カンタンお掃除かくし技!
掃除はめんどくさい・・やっぱり楽にお掃除したいですよね! 簡単お掃除ワザ&お得情報の記事数1000超え! きっとあなたのお役に立ちます!
[PR]
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
ごごナマ 知っトク!らいふ「禅寺直伝!掃除の技と心」ほうきと雑巾 2017年12月21日
NHKで放送されているお昼の生番組「ごごナマ 知っトク!らいふ」。
今回は曹洞宗八屋山普門寺の副住職の吉村昇洋さんが登場です。
吉村さんが「動」の修行とされる「掃除」について教えてくださります。
使う道具は「ほうき」と「ぞうきん」だけです。
掃除機などを使わなくても、基本をしっかりと押さえていればピカピカにすることができます。
【禅寺直伝!シンプル掃除術】
ほうきや雑巾を使うことで電気を使わずエコですし、ほうきや雑巾を使うことで見えてくることもあります。

<ほうきの極意>
◎穂先をまっすぐ立てて払うように掃く
毛先を寝かせるように掃いてしまうと、面で掃いているので細かなゴミが集まりません。
◎奥から入口に向かって掃く
ゴミが散乱しにくくなります。
◎ほうきのしまい方
穂先を上にして立てかかる・つるす
◎畳は目に沿って一方向に後ずさりしながら掃く
後ずさりをして汚れたところを踏まないようにします。
力を入れずにやさしく掃きましょう。
今はほうきを持っていないというご家庭も多いかもしれませんが、この機会に使ってみてもいいかもしれません。
私は小さなほうきを使っています。
掃除機を出すのが面倒なくらいのちょっとしたゴミを取るのならホウキがぴったりなんです。
まえよりもこまめに掃除ができるようになったと思います。
『掃除は心のちりを払う』
掃除というものは基本的に汚い状態ものをキレイにすることです。
汚い環境にいるとどうしても心は泡立ってしまいます。
心をスッキリするためにも、シンプルな状態に身を置くことが大切です。
<ぞうきんの極意>
◎ぞうきんをかたく絞るコツ
①濡らしたぞうきんを絞りやすい大きさにまとめ、右手をかえして手前の端を持つ。
②左手を前に向けた状態で、もう片方の端を持つ。
③右手をひねりながら下方向に動かし、左手もひねりながら上方向に上げていき絞る。
ですが、要はしっかりと絞れれば良いそうなので、自分のやりやすい方法でもかまわないとおっしゃってました。

◎永平寺仕込み!ぞうきんがけ
ぞうきんには両手をきちっとベタ付けする。
折り返す際は拭きムラができないように、行きで拭いたところと少しかぶせる。
◎階段のぞうきんがけ
①ぞうきんを縦に置き、片手をベタ付けする。
②もう片方の手はぞうきんの手前の端を持つ。
③階段を左右に1往復半拭いたら、下の段に降りて同じように拭く。
リズムよく行いましょう!
『ぞうきんで自分の心も磨く』
低い体勢でぞうきんがけを何十分と続けていると、次第に疲れも出てきて心が弱くなってきます。
そうなると少し手を抜いてもいいかな、楽してもいいかなと考えるようになってきますが、そこをグッとこらえて、キレイにしなければいけないものをちゃんとキレイにすることで、心の在り方も変わってきます。
『すばやく丁寧に』
ぞうきんがけをしていると、自分の弱くなる志向やいろんな思いが浮かんでくるんですが、それにとらわれないで、ただ掃除に意識を向けていきます。
その在り方を実践するためには素早くていねいにが大切になります。
<視聴者さんからの掃除の悩み>
◎トイレが汚れます。毎日掃除をしないとダメですか?
禅寺では修行僧のリーダーが毎日まず初めに掃除を行う重要な場所です。
①手拭き用のアルコールをトイレットペーパーに湿らせ、便座周辺を拭く。
雑巾を使うと汚染を広げてしまうことがあるので、使って捨てられるトイレットペーパーを使う方が衛生的です。

吉村さんのお寺のトイレには、トイレマットもスリッパもありません。
裸足で入っても大丈夫なトイレを常に作っておくためです。
◎来客が多くなる時期、玄関をきれいにしたい
じつは「玄関」という言葉は仏教用語なんです。
「奥深い仏道の入り口」という意味があります。
ですので、常にきれいにしておきたい場所です。
①置いてあるものをどかしてから掃除をする。
②たたきを奥から手前に向かってほうきがけする。
③上り口を奥から手前に向かってぞうきんがけする。
段差の部分は汚れが付きやすくなります。
④玄関の扉をぞうきんがけする。
桟があればそこも拭き掃除をします。
引き戸や鍵の部分についた手アカを拭き取ります。
ぞうきんがけは良い運動になりそうだなって思いました。
そして「ほうき」と「ぞうきん」だけの掃除・・
普段からこまめな掃除をして汚れをためないようにしておかないと難しいのかもしれない。
でもこれだけの道具で掃除ができたなら、シンプルでとってもはかどりそうかも。
●関連記事
ごごナマ 知っトク!らいふ「大掃除も怖くない!赤星流”小掃除術”」
ごごナマ 知っトク!らいふ「解決!気になる家の汚れ」セスキ水・トロトロ石けん
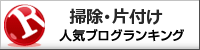

にほんブログ村
今回は曹洞宗八屋山普門寺の副住職の吉村昇洋さんが登場です。
吉村さんが「動」の修行とされる「掃除」について教えてくださります。
使う道具は「ほうき」と「ぞうきん」だけです。
掃除機などを使わなくても、基本をしっかりと押さえていればピカピカにすることができます。
【禅寺直伝!シンプル掃除術】
ほうきや雑巾を使うことで電気を使わずエコですし、ほうきや雑巾を使うことで見えてくることもあります。
 |
価格:1,361円 |
<ほうきの極意>
◎穂先をまっすぐ立てて払うように掃く
毛先を寝かせるように掃いてしまうと、面で掃いているので細かなゴミが集まりません。
◎奥から入口に向かって掃く
ゴミが散乱しにくくなります。
◎ほうきのしまい方
穂先を上にして立てかかる・つるす
◎畳は目に沿って一方向に後ずさりしながら掃く
後ずさりをして汚れたところを踏まないようにします。
力を入れずにやさしく掃きましょう。
今はほうきを持っていないというご家庭も多いかもしれませんが、この機会に使ってみてもいいかもしれません。
私は小さなほうきを使っています。
掃除機を出すのが面倒なくらいのちょっとしたゴミを取るのならホウキがぴったりなんです。
まえよりもこまめに掃除ができるようになったと思います。
『掃除は心のちりを払う』
掃除というものは基本的に汚い状態ものをキレイにすることです。
汚い環境にいるとどうしても心は泡立ってしまいます。
心をスッキリするためにも、シンプルな状態に身を置くことが大切です。
<ぞうきんの極意>
◎ぞうきんをかたく絞るコツ
①濡らしたぞうきんを絞りやすい大きさにまとめ、右手をかえして手前の端を持つ。
②左手を前に向けた状態で、もう片方の端を持つ。
③右手をひねりながら下方向に動かし、左手もひねりながら上方向に上げていき絞る。
ですが、要はしっかりと絞れれば良いそうなので、自分のやりやすい方法でもかまわないとおっしゃってました。
 |
価格:1,027円 |
◎永平寺仕込み!ぞうきんがけ
ぞうきんには両手をきちっとベタ付けする。
折り返す際は拭きムラができないように、行きで拭いたところと少しかぶせる。
◎階段のぞうきんがけ
①ぞうきんを縦に置き、片手をベタ付けする。
②もう片方の手はぞうきんの手前の端を持つ。
③階段を左右に1往復半拭いたら、下の段に降りて同じように拭く。
リズムよく行いましょう!
『ぞうきんで自分の心も磨く』
低い体勢でぞうきんがけを何十分と続けていると、次第に疲れも出てきて心が弱くなってきます。
そうなると少し手を抜いてもいいかな、楽してもいいかなと考えるようになってきますが、そこをグッとこらえて、キレイにしなければいけないものをちゃんとキレイにすることで、心の在り方も変わってきます。
『すばやく丁寧に』
ぞうきんがけをしていると、自分の弱くなる志向やいろんな思いが浮かんでくるんですが、それにとらわれないで、ただ掃除に意識を向けていきます。
その在り方を実践するためには素早くていねいにが大切になります。
<視聴者さんからの掃除の悩み>
◎トイレが汚れます。毎日掃除をしないとダメですか?
禅寺では修行僧のリーダーが毎日まず初めに掃除を行う重要な場所です。
①手拭き用のアルコールをトイレットペーパーに湿らせ、便座周辺を拭く。
雑巾を使うと汚染を広げてしまうことがあるので、使って捨てられるトイレットペーパーを使う方が衛生的です。
 |
価格:500円 |
吉村さんのお寺のトイレには、トイレマットもスリッパもありません。
裸足で入っても大丈夫なトイレを常に作っておくためです。
◎来客が多くなる時期、玄関をきれいにしたい
じつは「玄関」という言葉は仏教用語なんです。
「奥深い仏道の入り口」という意味があります。
ですので、常にきれいにしておきたい場所です。
①置いてあるものをどかしてから掃除をする。
②たたきを奥から手前に向かってほうきがけする。
③上り口を奥から手前に向かってぞうきんがけする。
段差の部分は汚れが付きやすくなります。
④玄関の扉をぞうきんがけする。
桟があればそこも拭き掃除をします。
引き戸や鍵の部分についた手アカを拭き取ります。
ぞうきんがけは良い運動になりそうだなって思いました。
そして「ほうき」と「ぞうきん」だけの掃除・・
普段からこまめな掃除をして汚れをためないようにしておかないと難しいのかもしれない。
でもこれだけの道具で掃除ができたなら、シンプルでとってもはかどりそうかも。
●関連記事
ごごナマ 知っトク!らいふ「大掃除も怖くない!赤星流”小掃除術”」
ごごナマ 知っトク!らいふ「解決!気になる家の汚れ」セスキ水・トロトロ石けん
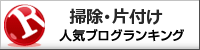
にほんブログ村
PR
ブログ内検索
掃除したい物や場所を検索して下さい(*‘∀‘)/
最新記事
(07/02)
(06/04)
(05/08)
(05/06)
(04/11)
カテゴリー
プロフィール
HN:
お掃除娘
性別:
女性
自己紹介:
苦手な掃除を手抜きしていても、ちゃんとキレイにしたい欲張りな私のお掃除探究ブログです。

COMMENT